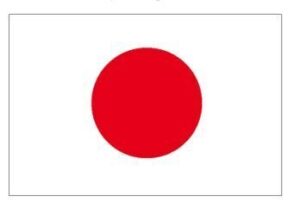阪神甲子園球場



阪神甲子園球場の特徴・魅力
高校球児の夏の思い出を刻む全国高校野球選手権大会の決勝戦の舞台であり、阪神タイガースの本拠地として「六甲おろし」の合唱が響く球場でもある、阪神甲子園球場。兵庫県西宮市に1924年に開場し、数々のドラマにより、今や日本最古の現役野球場として唯一無二の存在である。
最寄り駅から徒歩約3分、約47,000人の収容人数を誇り、改修やLED照明導入により快適性を向上させつつ、深い緑の蔦が覆う外壁や黒土と天然芝のグラウンドは、今も昔の面影を守り続けている。
阪神甲子園球場の特徴
兵庫県西宮市に1924年開場。日本最古の現役野球場、阪神甲子園球場。高校野球と阪神タイガースの本拠地として知られる。外壁を覆う蔦は甲子園球場の象徴であり、2009年に全国の高校から苗を集め再植樹された。グラウンドは黒土と天然芝で、芝は二毛作により通年緑を保つ。
収容人数は約47,000人。2008~2010年に改修され、2022年にLED照明を導入。最寄り駅から徒歩約3分で、授乳室や多目的トイレなどの設備も整う。
阪神甲子園球場の魅力
1924年に開場以来、重ねられてきた数々のドラマチックな試合により、阪神甲子園球場は特別な存在として野球ファンを惹きつけてやまない。高校野球では試合で負けた選手はグラウンドの黒土を持ち帰る。
阪神の熱戦ではアルプススタンドからの熱狂的な応援や「六甲おろし」の合唱をする。その深い感動の集積と、球場の外観を彩る蔦が一体となって、唯一無二の魅力となっている。
阪神甲子園球場へのアクセス
球場へは、阪神電鉄本線「甲子園駅」から徒歩約3分とアクセス良好。大阪方面からは梅田駅より阪神本線で約20〜30分、京都方面からは阪急電鉄を経由し梅田乗り換えで約1時間が目安。伊丹空港からはリムジンバスが運行しており、所要時間は約40分である。
球場周辺にはタクシー乗り場が複数あるが、試合終了後などの混雑時には長時間待たされることが多く、公共交通機関の利用がオススメだ。
阪神甲子園球場の施設概要
開場時間
阪神甲子園球場の開場時間は、試合開始の約2時間前が目安。たとえば18時開始の試合では、16時に開門されることが多い。イベントや試合によって異なるため、事前に公式サイトでスケジュールを確認しておきたい。
収容人数
阪神甲子園球場の収容人数は最大47,508人で、日本の野球場の中でも屈指の規模を誇る。
座席表
甲子園球場の座席は、プレミアムシート、アルプス席、外野席など多彩に分かれており、座席表は公式サイトでPDF形式で確認できる。座席ごとの見え方や段差、応援スタイルの違いもあるため、観戦スタイルに合わせた選択が重要である。車椅子席の案内も充実している。
グルメ・ショップ
球場内には甲子園カレーやジャンボ焼鳥、監督・選手とのコラボメニューなど、個性豊かなスタジアムグルメが揃う。外周では期間限定のフードイベントも開催され、観戦以外の楽しみも充実。グッズショップでは応援アイテムや限定商品も入手可能だ。
利用案内
阪神甲子園球場へは阪神電鉄「甲子園駅」から徒歩約3分。チケットは公式サイト「甲チケ」やコンビニ、窓口で購入可能。座席は内野、アルプス、外野席など。売店では限定グルメも楽しめる。トイレは清潔で多目的対応。缶・ビン類の持込禁止。開門は試合開始の約2時間前が目安となる。
チケット購入方法
阪神甲子園球場のチケットは、公式サイト「甲チケ」やコンビニ、プレイガイドなどで購入可能である。人気試合は早期に完売することもあるため、先行販売やファンクラブ枠の活用が有効である。座席指定や空席情報の確認もオンラインでスムーズに行える。
注意事項
球場には缶・ビン類の持ち込み禁止、スタンド内禁煙、応援エリアのルール遵守など、観戦マナーが定められている。ライト外野席は阪神専用応援席として制限があるため、服装や応援グッズにも注意が必要である。安全で快適な観戦のため、事前確認が望ましい。
阪神甲子園球場の近隣スポット情報
周辺には、球場併設の「甲子園歴史館」(徒歩約1分)で名選手の記録や展示が楽しめるほか、「ららぽーと甲子園」(徒歩約5分)では観戦前後の買い物や食事に便利。地元で人気の「じゃじゃ旨」(徒歩約5分)では関西風お好み焼きが味わえる。野球観戦とあわせて立ち寄りたいスポットである。
スポット情報
- 住所兵庫県西宮市甲子園町1−82
- TEL079-847-1041
- アクセス
① 三宮駅 - JR神戸線 約15分 - 西宮駅 - 阪神本線 約5分 - 甲子園駅 - 徒歩 約3分
② 大阪梅田駅 - 阪神本線 直通 約20分 - 甲子園駅 - 徒歩 約3分
③ 東京駅 - 東海道新幹線 約160分 - 新大阪駅 - JR神戸線 約15分 - 西宮駅 - 阪神本線 約5分 - 甲子園駅 - 徒歩 約3分
- その他

- 取材・文:
- Journal ONE( 編集部 )