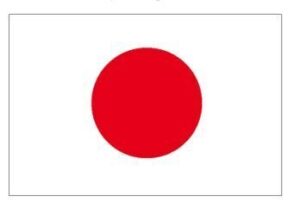福岡大大濠の榎木‐永塚和志撮影
福岡大大濠で背負った重圧と榎木の人間性
例えば1年生の白谷などが優勝直後に無邪気に喜んだり、他の3年生選手が歓喜にむせび泣くのとは異なって、榎木の表情にはどちらかといえば安堵のそれが見て取れた。
1年生から起用をされてはいたものの、司令塔というポジション柄もあり、常勝の看板を立てかけるチームでプレーをする重圧から「逃げたくなる時もあった」という。2024年のウインターカップが終わってからの1年間においてもチームを十全に牽引できず「暗闇の中」に陥る感覚を味わった。
それでも、いつしか片峯コーチから「このチームのガードはお前だ」という言葉をもらったことで、自信を得られるようになっていった。
榎木の話しぶりを聞いていると、彼がいかにも聡明で実直な人物であるかわかる。加えて、彼がバスケットボールという競技に対して愚直に取り組んでいるかもわかる。そして、そのことが彼の人間としての魅力となっているようにも感じられる。

優勝会見でマイクを持つ榎木と片峯コーチ‐永塚和志撮影
福岡大大濠で戦う意味と榎木の覚悟
常勝だと言われる。溢れんばかりの才能を集めた集団だと言われる。人々は福岡大大濠を勝って当然で、その選手たちは活躍して然るべきだという目で見る。
一方で、169cmという身長は競技の上で「凡」であるどころか、不利ですらある。しかし、逃げたくなることはあっても、実際には逃げずに、もがいた。だからこそ、決勝戦では報いを享受できたのだ。
決勝の相手・東山と佐藤凪
東山にとっては、3度目のウインターカップ決勝戦。三度、敗れた。東山のPG、佐藤凪の肉体が万全から遠いところにあったのは、如実だった。絶対的中心選手は前日の準決勝で、39分以上、コートに立ち続けた。下がったのは最終盤。ベンチに戻った彼は椅子に座った。倒れ込んだとしてもいい。実際の音は聞こえなくとも、どさっと音をたてていたに違いないと思わせる様子だった。
そんな佐藤について、東山の大澤徹也コーチは「あいつはオーバーなので。ああいう風に見せて、油断させて、明日はピンピンしてやるかもしれませんので」と笑顔で語っていた。それは傷ついているように見えるエースを、指揮官として大丈夫なんだ、大丈夫であってほしいと願う物言いに聞こえなくもなかった。
「今日は立っているのもままならないくらいフラフラだった」。
決勝戦に敗れた後、大澤氏はこのように話した。準決勝後の言葉がブラフだったとすれば、もはや試合のない決勝戦の後にそれをかける必要はなかった。
最後は敗者としてコートを去った佐藤。しかし、大会の立役の1人だったことに異論は多くあるまい。それが安直なものだとは理解しながらも、決勝戦の構図が佐藤対福岡大大濠だったことに異論を挟むことはできなかった。

決勝戦で戦い続けた佐藤凪(東山高)‐永塚和志撮影
東山のガード文化と佐藤凪
岡田侑大(島根スサノオマジック)、米須玲音(川崎ブレイブサンダース)、瀬川琉久(千葉ジェッツ)。偉大な選手を輩出してきた東山に来た時からそれは覚悟の上だった。――あるいは臨むところだった――だろうが… それゆえ、佐藤もまた容赦なく背中にのしかかる重圧と向き合ってきたに違いない。
両手から放たれるノールックのパスが決まるとその都度、会場が低い声でどよめいた。唸った。日本で最高峰の舞台においても大半が持ち得ない才を見せる。ガードを中心としたチーム作りにこだわりのある大澤コーチ。そこには、得点能力という現代バスケットボールにおけるPGに必要な要素も刷り込ませてきた。
平均20.3得点、9.3アシスト。弧の高い3Pシュートは6試合で41本(平均6.8本、成功率は22%だった)放った。大澤氏は佐藤に得点の意識を持たせたことでよりプレーの選択肢を有する選手になったと述べた。
学生スポーツにおいて指導者が多くの選手を抱えそれぞれに目をかけなければいけない。それゆえ、1人の選手について過度に言及することは多くない。しかし、それでも大澤コーチはより完成度の高いPGに成長した佐藤についてこう語る。
「東山で何十年とやらせていただいていいますけども、凪に関しては私の理想のガードじゃないかと思っています」と。

「理想のガード」と言わしめる佐藤凪‐永塚和志撮影

「X」アカウント https://x.com/kaznagatsuka