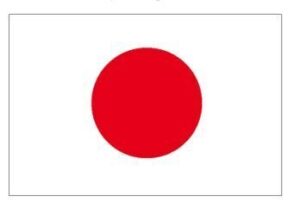このスタジアムはインゴールからスタンドまで距離があるので、ネットが張っていない。従って、コンバージョンキックやペナルティキックでゴールを狙う際、選手の蹴ったボールが数バウンドしてスタンドインするのだが、そこへ子供たちが群がるのである。これは芝生席ならではの光景であろう。キックのたびに嬉々と走り回る子供たち。これまた古代イングランドの村祭り的情景である。

ゴールから距離があるためネットなどの障害物もない‐平床大輔撮影
試合の方は、ダイナボアーズが先制トライを決め、ホームの観客を大いに沸かせるも、その後は前半風上に立ったブレイブルーパスのペースで進む。それにしてもモウンガのプレーが美しい。
絶妙なタイミングで繰り出す巧みなタッチキックにしろ、躍動感溢れるラインブレークにしろ、そのどれもが芸術品レベル。しつこいようだが、これで2,000円は超お買い得だ。外国人選手枠やその他の運営も含め、リーグワンには是非、これからも現在の興行レベルを維持してもらいたいものである。
では、ここで相模原ギオンスタジアムで観るダイナボアーズ戦の優れたポイントを2つ紹介しよう。第1に、このスタジアムは場内アナウンスが秀逸である。ペナルティやタッチキックなどでプレーが止まると、すかさずアナウンスが入り、状況やペナルティの説明をするだが、この解説が親切で大変分かりやすい。
しかし、それでいて適度な尺にまとめられているので、ルールを知っている人の邪魔にならない。ラグビーは観に行ってみたいけれど、ルールがそこまで把握できていないので二の足を踏んでいる人は来季、目指すべきはギオンスタジアムである。もちろん、相模原の方の。

地元の大歓声を受けた相模原DB(写真は静岡BR戦)-Journal-ONE撮影
そして2つ目のポイントは、ダイナボアーズボールのスクラムで流れるBGM。ホームチームのマイボールスクラムで毎回、中世ヨーロッパ風のラッパのメロディが流れるのだが、これがラグビーの醍醐味であるスクラムを盛り上げるのに一役も二役も買っていて良いのである(後になって調べてみると、これはブラスタージャックス&ティミー・トランペットの”ナルコ”という曲であることが判明)。
ビジターチームのノックオン(あるいはその他の軽い反則)、ラッパ、スクラムという流れには、ある種の痛快さがあり、楽しい中毒性がある。一度、ブレイブルーパスボールのスクラムで誤ってBGMを流しかけ、慌てて再生を停止する一幕もあったが、その辺のアナログ感も微笑ましくて良かった。
チーム史上最多観客動員数を更新
試合は風上でプレーした前半に大量リードを築いたブレイブルーパスが、風下となった後半の序盤にギアを上げ、先にトライを決めて試合の行方を決定付ける。この辺のマネージメントは、さすがディフェンディングチャンピオンと唸らされる。どうやら試合の大勢が決したように思われた後半15分過ぎ、気になっていた芝生席へ移動してみることにした。
やはり、フィールドとは距離があり、俯瞰で見られないので、状況は把握しづらいが、目線がほとんどフィールドレベルなので、意外と臨場感はある。それに、寝転がって見られるのが良い。芝生に横たわり、生ビール飲みながらラグビー観戦というのも、それはそれで乙である。「どうだ、ざまあみろ」、とでも言ってやりたくなるだろう(誰に向かってかは分からないが)。
結局、試合はビジターチームが45-28で勝利。それでも、ダイナボアーズも後半、3トライ3ゴールを決め、しっかりとホームの観客を沸かせていた。なんでも、後半途中に流れた場内アナウンスによると、この日の来場者数は8911人で、ダイナボアーズとしてはリーグワンにおけるチーム史上最多観客動員数を更新したのだとか。やはり、ゴールデンウィークの相模原は正解だったのである。

帰路、スタジアム付近の農村風景∸平床大輔撮影
帰路は距離的に原当麻とそう変わらない”下溝駅”まで歩いてみることにした。スタジアムを出ると、しばらくは畑と、その向こうに林が続いていて、かつてよく訪れた八重山の農村を彷彿とさせる風景が広がる。都市部で生まれ育ったのに、こういう風景に懐かしさを感じるのだから、不思議なものである。もしかしたら農耕民族のDNAには、そういうノスタルジアが組み込まれているのかもしれない。