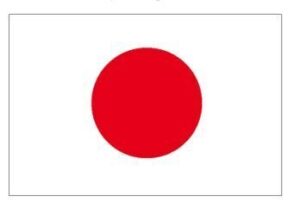Bリーグドラフトは、Bリーグが掲げる「B改革」の象徴として実施された。すなわち、リーグ構造の転換と戦力均衡の実現に向けた新たな取り組みだ。本稿では初開催となったイベントの実像、その熱気、課題、そして未来像を追う。
会場の雰囲気とドラフト演出
全体的に照明が暗く落とされた会場の雰囲気は、さながら劇場を思わせた。漂う荘厳な空気は、足を踏み入れる者の身を引き締めた。
「入った瞬間、これから指名される選手のことを考えるとより緊張感が高まりました」。
イベント終幕後、長崎ヴェルカの代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーの伊藤拓摩氏はこう話した。その場で覚えた高揚感がまだ完全には覚めきらないといった様子で笑顔を見せていた。
イベントとは、1月29日に東京ドームシティホール・Kanadevia Hallで行われたBリーグドラフトのことだ。同リーグでは2026-27よりリーグ構造とライセンス基準の抜本的改革である「B改革」と施す。これまで「B1」と呼ばれてきた最上位カテゴリーは「Bプレミア」となって新たな出発をする。
ドラフトはそれに伴ったもので、原則として戦力均衡に主眼を置いたものとなる。これまで選手は自由に所属先を選択することができた。しかし、今後はBプレミアでのプレーを望む日本人の若手(みなし日本人を含む。対象は高校3年生~大学4年生+プロ2年目まで)はドラフトを経ることでしかそれを実現することはできない。
因みに、下位カテゴリーの「Bワン」「Bネクスト」はその範疇ではない。

緊張感漂うBリーグドラフト会場-永塚和志撮影
ドラフト制度導入の“もったいなさ”とBリーグの挑戦
日本でドラフトというとプロ野球(NPB)の印象が色濃く毎年、注目が集まる。
一方で、イベントとしてこれを見た時、会場や運営方法のフォーマット等はほぼ固定されている。これは、やや保守的に感じられる。加えて、同ドラフトの1巡指名は成績下位チームから選択していく「ウェーバー方式」は非採用だ。そのため、1人の選手に複数球団の指名が重なった場合にはくじ引きによって交渉権が決まる。
これ自体は面白いものではある。しかし、戦力均衡という視点において機能をしているとはいえない。
いずれにせよ、日本において実質ナンバー1のプロスポーツであるNPB。その実態を鑑みれば、ドラフトのイベントとしてのあり方にはある種の「もったいなさ」を感じる人もいるのではないか。
その点、Bリーグは明らかにドラフトを「一大イベント」にしていくという目論見がある。劇場を思わせる会場のセッティング。(このあたりは同様の会場を使用してきた「Bリーグアワード」等から得てきた経験が生きていそうだ)
加えて、島田慎二チェアマンが壇上から指名を読み上げ選手に帽子を被せるといった演出。これらは、世界最高峰・NBAを参考にしている部分も多分にあるだろう。

全体2番目指名で茨城ロボッツから指名を受けた赤間賢人‐永塚和志撮影
エントリー選手の不足と指名数の少なさ
もっとも、今回のドラフトが十全に盛り上がったかといえば、そうはならなかった。最大の理由はエントリーをした選手に「目玉」や「スター」が乏しかったことが挙げられた。ドラフトが始まるのを前に、今シーズンは多くの大学等の名のある有力選手らがすでにBリーグのチームに「駆け込み」で加入をしてしまっていた。
結果、今回のドラフトで名前を呼ばれた選手の総計はわずか11名にとどまった。(1巡が6名、2巡が2名、3巡が3名)
会場には18名の有力指名候補選手が招待されていた。しかし、残酷にもうち7名は指名を受けることがなかったのだ。

富山グラウジーズから3巡指名を受けた泉登翔‐永塚和志撮影
サラリーキャップ、ドラフトのジレンマ
ドラフトの開始にともなって1巡指名選手には1800万円が、2巡指名選手には1400万円(ともに2年契約プラス1年の選手オプションの場合)の年俸を支払う規定も設けられていた。
Bプレミアでは、こちらも戦力格差の縮小するために各チームには下限5億円、上限8億円の「サラリーキャップ(選手の年俸総額)」が導入される。
選手に投じられる予算に制限がある中で原則、プロの経験のない選手たちにそれだけの年俸を投資するという勇気を、チーム側とすれば振り絞りにくかった側面もあったはずだ。

「X」アカウント https://x.com/kaznagatsuka